© 新しい日常を創るためのベースキャンプ All rights reserved.

PTA役員決めの苦悩─役割を担う喜びを忘れた大人たち
もうすぐ子どもたちは新学期。親たちは「PTAの役員決め」の季節です。
誰も挙手しない。口も開かない。沈黙のなか30分──こんなPTA決めの場面が、日本中で繰り広げられます。
子どもを学校に通わせている保護者にとって、大きな問題です。
PTAの「役員決め」という地獄絵図
PTAも町内会・自治会も、「入退会自由な民主的組織」として、身近なものだろう。
しかしその大部分の実情は「民主的」からはほど遠い。役割の強制、我慢の分配、それを拒否するものは悪──近年よく報道されるように、こんな考え方が支配的だ。
そして、役割を担うことの喜びを知らない親たちが増え、そういう親たちは、我が子が役割を担うことを快く思わない。
「あと一押しで、やってくれそう!」という方には、選考委員全員(10人)でご自宅を訪問し、頭を下げてお願いしたこともあります。
(東洋経済ONLINE「PTAでいちばん大変!“役員決め”の舞台裏」)
東洋経済ONLINEに、「PTAでいちばん大変!“役員決め”の舞台裏」という記事が載っていた。PTAの「次期役員を見つける」という役割を担う「選考委員」という制度を紹介しながら、PTA役員決めの過酷な実態をまとめた記事だ。PTAの役員決めが大変すぎて、各地で「異常事態」が起こっているというニュースは、新聞やTVなどでも繰り返し報じられている。
PTAに限らず、同じような状態は、町内会・自治会にも広くみられる。PTAも町会も、もちろん前向きな気持ちでみんなでやっているところもあるのだろうが、残念ながらそれはレアケースだろう。
子どもたちが「◯◯係をやりたくない」と言う理由

- *企画を進行する企画担当の子どもたち

- *進める側だけでなく話を聞くのも上手
れんげ舎の子どもの活動では、「子どもの自治」が大切にされている。これは、だれかの「これをやりたい」というアイデアを発端に、みんなで話し合い、計画し、役割分担しながら準備し、実行していく。子どもたち自身の力で進んでいくのが、この活動の特徴だ。
つい先日も、神奈川県の施設で1泊2日の行事をやった。15人の子どもたちが3つの班に分かれて、それぞれの担当企画を準備して楽しんだ。たったの1泊2日だけれど、密度の高い楽しい時間だった。
こういう企画を実行するためには、アイデアも、話し合いも、役割分担も必要だ。小さなものから大きなものまで、様々な役割があり、みんな「◯◯係やりたい」「わたしは◯◯を担当したい」と、とても積極的だ。自分たちのやりたいことを自分たちで進めていくのだから、そこには楽しさがいっぱいにつまっているのだ。
なにかの「役員決め」ともなれば、次々と手があがって、決めるのにも一苦労。親たちのPTAとは、正反対の状況が繰り広げられる。
子どもが役割を担うことを忌み嫌う親たち
ただ、近年は気になることがある。例えばなにかの係とか委員みたいなのを決めるときに、躊躇する子どもが増えてきたのだ。
以前は、「◯◯係やりたい人は?」と尋ねると、大勢の子どもが手をあげていた。決めるのも大変だった。それが、「う~ん、やりたいけど…どうしよう?」と困った顔をする子が増えてきたのだ。
子どもたちからよく事情を聞いてみると「なにかの係や役員になることを、親が喜ばない」という理由があることがわかった。20年前だったら、子どもがなにかの係になると、親たちは「がんばって!」「責任があるんだから、ちゃんとやるんだよ」などなど、表現はいろいろでも、たいていは子どもを励ましていたものだ。ところが、最近は違う。
「え、係になったの? できるの? やめたら…?」
親たちを批判しているのではない。これは「最近の親は子どもを励まさない」ということではないのだ。背景にあるのは、昔もいまも変わらない子どもにしあわせになってもらいたいという親心だと思う。
親たちはおそらく、自分自身がPTAで役割を担って辛い経験をしたり、あるいはそういう場面を目撃したりしたのだろう。生産的な話し合いの経験が乏しく、なにかの役割を引き受けて喜びを感じたことがないのだろう。いや、子どもの頃は違ったはず。でも、いまは喜びを忘れてしまったのかもしれない。子どもたちに、役割を担うことで嫌な思いをせたくないのだ。論理的にどうこうというより、生理的な拒否感を抱いているように見える人もいる。
ともあれ親たちは、我が子のためを思って「◯◯係をやりたい? やめたら?」と声をかける。
役割を担うことは人生の喜び
でも、忘れてはならないのは、役割を担うことには、喜びがあるということだ。
子どもたちは、あそびや様々な活動のなかで自然に役割を担おうとする。しかし、親の組織であるPTAでは、そうなっていない。子どもが大人に育っていく課程で、役割を担うことの喜び、自治の喜び、誇りなどが、生活のなかから忘れ去られていく。
PTAも町内会・自治会も、もともと「それがあることが豊かさにつながるから」存在している。でも、「入退会自由な民主的組織」という原則は、深く深く形骸化している。
「PTAをもっとよくしたい」
「地域をもっとよくしたい」
こうした純粋な気持ちから、それら諸活動に参加し、改革を試みて玉砕する。傷つき、疲れ果て、二度とそういう現場には戻らない。僕はそういう人たちを、大勢知っている。
講演先などでも、よく言うのだ。「PTAや町内会・自治会の改革はプロの領域。まずは自分で小さな場をつくって、運営するところからはじめてみませんか?」と。
選挙になると急に投票を呼びかけ、それこそが民主的で善良な行為であるかのような空気感が、ここ数年で急にできあがってきた。しかし「民主主義」というのは、そういうレベルの問題だろうか。 責任を取らされるのではなく、自ら負うという人生への参画。日常のなかの民主主義の成立を、もっと大切に試みたい。
*自分で「場」をつくりたい人を応援するメルマガ「場づくりのチカラ」
*自分で「場」をつくりたい人のための学びの場「場づくりクラス」
Comments
コメント
この記事へのトラックバックはありません。

仲間がどんどん減っていく! 対処法は「客体化プロセス」を変換すること
共に活動していた仲間が抜けてしまう。 活動していると、仲間が去るのは避けられないことですが、中心で活動を支えている人には、なかなかつらい…














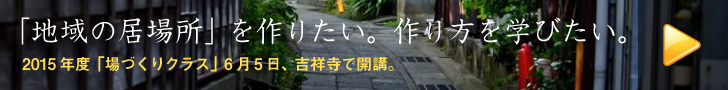




この記事へのコメントはありません。